
今回は、粘着ラバーの手入れ方法について解説していきます。
粘着ラバーは一般的なテンションラバーとは性質が違うため、手入れの方法も変わってきます。
そして、手入れ次第で性能が変わるのが粘着ラバーです!
では、どのように手入れすればいいのでしょうか。
詳しく解説してきます!
手入れ次第で性能が変わる
まず、粘着ラバーは手入れ次第で性能が変わるラバーです。
具体的には、
- ラバクリをするかしないか
- 保護シートを貼るか貼らないか(貼るとしても、どの保護シートを貼るか)
の2点によって、性能が大きく変わります。
そして、あなたが粘着ラバーに求めているものが何かによって手入れの方法が変わってくるので、
正しい手入れ方法は、人それぞれ違うものになります。
この記事で、是非あなたに合った手入れ方法を見つけてください!
基本の手入れ方法
まずは、中上級レベルの粘着ユーザーで最も多いであろう、基本となる手入れ方法をお教えします!
それは、練習中や練習後にラバーに息をかけて手で拭い、非粘着の保護シートを貼る!です。
息をかけるというのは、プロもよく試合中にしている、はぁーと吹きかけるものです
この手入れ方法の特徴は、粘着力が増さないというところです。
粘着力というのはあればあるほどいいというものでもなくて、
粘着力が増すと回転量は上がるのですが、スピードや飛距離が落ちてしまいます。
そして、粘着ラバーはもともとかなり回転重視のラバーなので、もともと以上に回転力を上げる必要性があまりありません。
したがって、この手入れをするとスピードとスピンのバランスがよくなるため、
一般的にはこの手入れ方法が基本です!
私自身も、粘着ラバーを使うときはこの息をかける+非粘着の保護シートです。
ラバクリはべたつく
次に、練習後にラバークリーナーをかけるという手入れ方法です。
これをすると、粘着ラバー表面がべたつきます。
このべたつきというのが、そもそもの粘着とは少し違うもので、ラバクリをすると水気を含んだべたつき方をするようになります。
粘着ラバー本体の粘着をぺちゃぺちゃとして、ラバクリをした粘着ラバーはべたべたです。
このべたべたのラバーは、基本的にあまり弾まず、ラバーの表面でスリップすることも増えます。
つまり、粘着ラバーにラバクリはあまりよくありません・・・
基本的には、ラバクリの代わりに息をかけるようにしましょう。
保護シートの手入れ
粘着保護シート
ここからが個人的な好みが出るところです。
まず、粘着保護シートを貼って保存すると、表面の粘着力がさらに増します。
つまり、回転量が上がって弾みが落ちるということです。
これにより、しっかりとスイングしても速い球が出にくいため、
粘着ラバー特有の癖玉がより強化されます!
イメージとしては、開封直後の粘着力が強い状態に近づく感じです。
ツッツキにせよ、ドライブにせよ、相手は予想外の遅さに戸惑うことになります(笑)
さらに、弾みが低くなるため、ストップやブロックがとても止まりやすくなります。
なんなら、ツッツキのつもりで振ったものがストップになることが多々あります(笑)
しかし、もともと弾まない粘着ラバーがさらに弾まなくなるため、粘着保護シートを貼って保存していると本当に弾みません(笑)
なので、スピードが極端に遅くなるため、一般的な攻撃型の選手にはあまり向きません。
粘着ラバーを使ってツッツキからのカウンターではめプレーをしている方なんかにはドンピシャの手入れ方法になります!
吸着保護シート
次に、吸着保護シートを使って保存する方法です。
まず、この方法で粘着ラバーを保存している人はあまりいません。
しかし、実際には十分ありな方法なので、解説していきます。
粘着ラバーを吸着保護シートで保存すると、ラバーの粘着力が少し落ちます。
これは、吸着シートに粘着力を吸い取られるからです。
これによって、回転量は落ちるけど弾みやすい粘着ラバーが完成します。
とはいえ、粘着ラバーはもともとの回転量がとんでもなく高いので、落ちると言ってもテンションラバーよりはかかります。
そして、弾みやすいと言ってもそこはテンションラバーにはかないません。
つまり、吸着保護シートを使うと少しテンションラバーに近い粘着ラバーが完成します。
非粘着の保護シート
これはすでに軽く紹介しましたが、
非粘着の保護シートは、保護シートの中で唯一性能に関与しません。
それでいてラバーの保護はしてくれるので、
寿命は延ばしたいけど性能に影響を与えてほしくないという方にはこの非粘着の保護シートがおすすめです。
まとめ
結論としては、粘着ラバーにはラバクリは使わずに息を吹きかけるようにすること。
そして、回転と弾みの調整を保護シートの種類で行うことでそれぞれに合ったラバーが完成する!
ということになります。
粘着ラバーはそもそも弾まないラバーなので、基本的には非粘着の保護シートを使うことでむやみに粘着力を上げないのがおすすめです。
今回の記事を参考に、是非自分に合った手入れを見つけてください!
関連記事


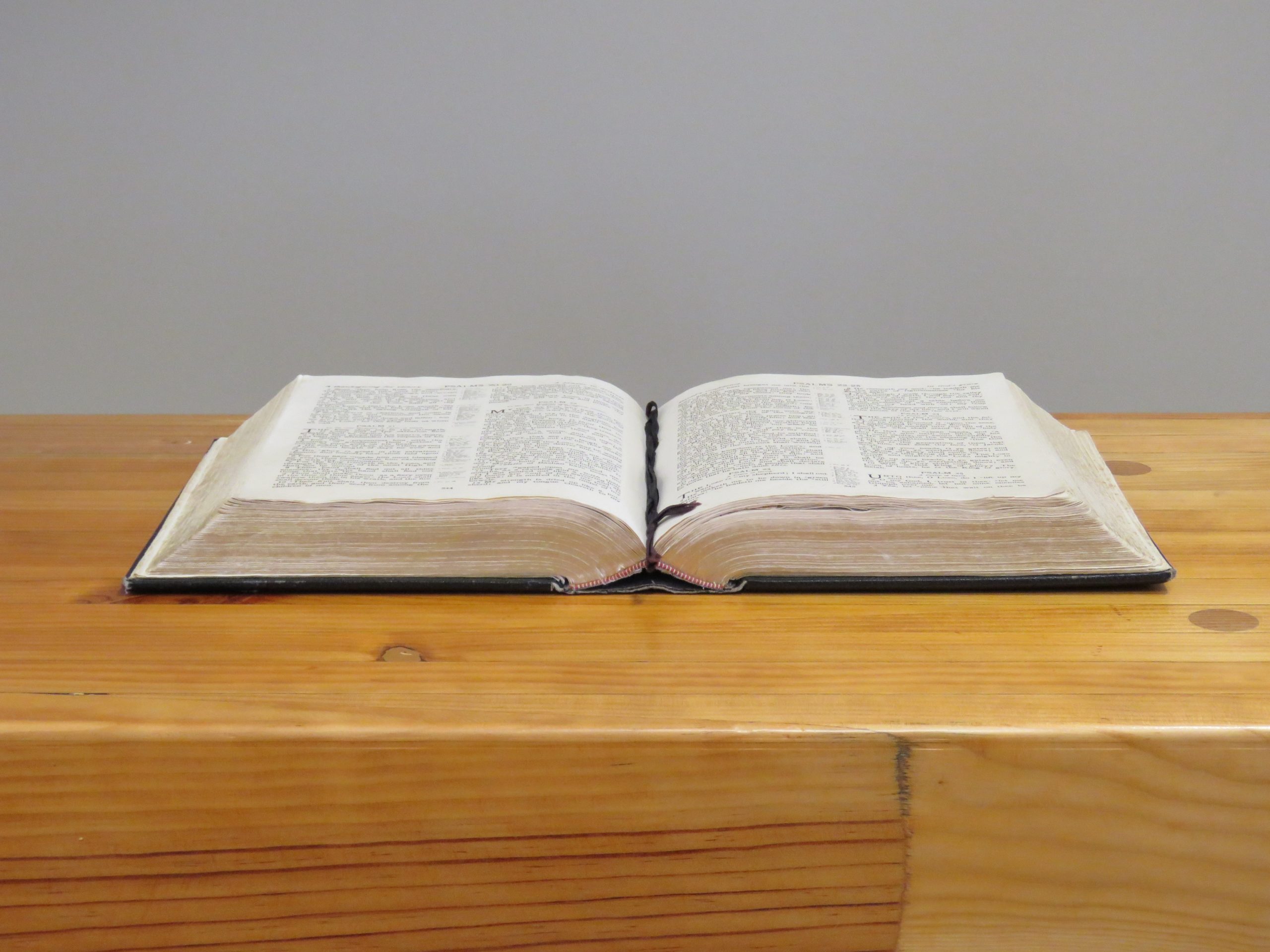
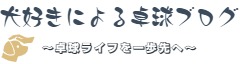




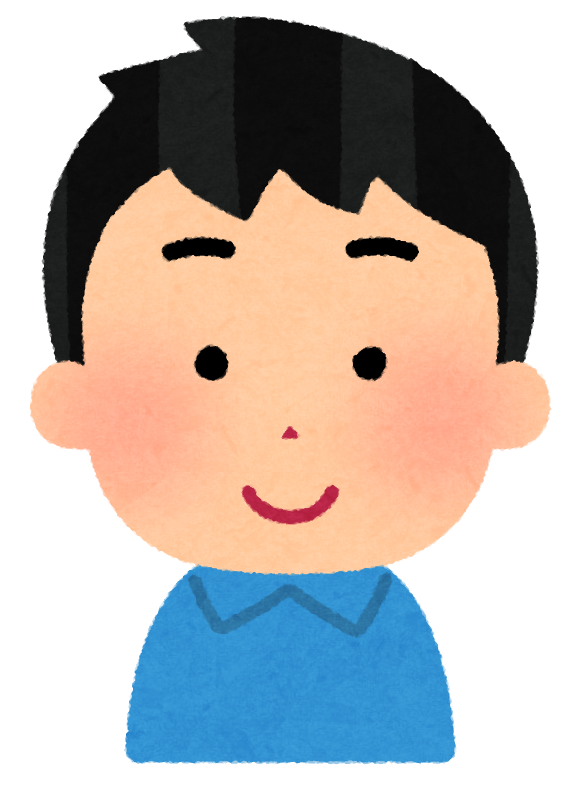
コメント
[…] 手入れ次第で大きく性能が変わる粘着ラバーの正しい手入れ方法 […]